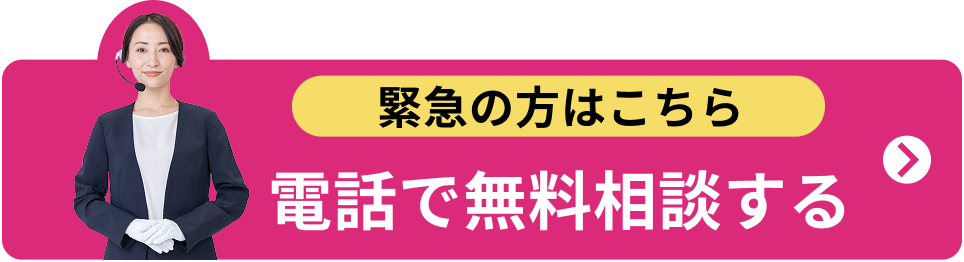
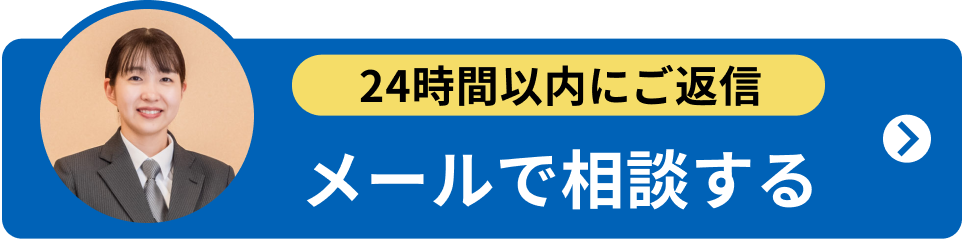

一般葬・家族葬
直葬・お別れプラン
市民葬
法要プラン

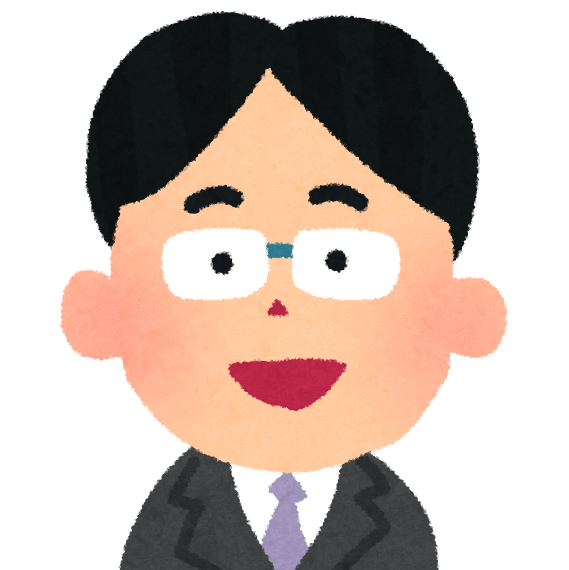 京王メモリアルスタッフ
京王メモリアルスタッフこんにちは!京王メモリアルのスタッフです。
いつも私たちのコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、以前のコラムでも少し触れた「六曜」について、特に「友引」に焦点をあてて詳しくお話しさせていただきたいと思います。
六曜は、日本の古くから伝わる暦注(こよみのちゅう)であり、現在も日常生活のさまざまな場面で参考にされることがあります。
特に葬儀や結婚式などの行事を行う日取りを選ぶ際には、多くの方が六曜の影響を気にされるのです。
では、まずは基本に立ち返り、六曜の種類とそれぞれの意味について振り返ってみましょう。
著者|


京王メモリアル 葬祭ディレクター
「六曜」とは、先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぶ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっこう)の六種類の暦注のことをいいます。
それぞれに特徴的な吉凶を示す意味合いを持っており、日本の伝統的な暦の一部として、特に儀式や行事の日取りを決める際の参考になっています。
●先勝(せんしょう、さきかち)
先勝は、名前の通り「先んずれば勝ち」という意味を持っています。この日は、何事も早めに済ませておくことが良いとされ、行動を開始するのに適した日と位置付けられています。
具体的には、一日の中では午前中が特に吉とされ、朝の時間帯に重要な用事を済ませるのが良いとされています。一方、午後は凶とされることが多く、午後に物事を始めるのは避けるのが無難とされています。
●先負(せんぶ、せんぷ、さきまけ)
先負は、先勝の反対の意味合いを持ち、「先んずれば負ける」という考え方からきています。つまり、何事も急ぎすぎると失敗する可能性が高いため、午前中は静かに過ごし、重要な決定や行動は控えるのが良いとされます。
逆に午後は吉とされることが多く、時間に余裕を持って行動するのが理想的です。
●仏滅(ぶつめつ)
仏滅は、「仏が滅する日」と直訳でき、その字面の通り、一日を通じてあまり縁起の良くないとされる日です。特に、新しいことを始めたり、祝い事を行うのは避けるべき日と考えられています。
結婚式や開店などのお祝いを延期するケースも多く、日本の伝統的な文化の中では、やや忌避されることが少なくありません。
●大安(たいあん)
大安は、「大いに安し」の意味を持ち、一日を通じて最も縁起の良い日とされます。何事を始めるのに適しているとされ、結婚式や縁起を担ぐ儀式に選ばれることが多いです。
また、葬儀においても問題なく行われる日とされ、縁起の良さから選ばれることが多いです。ただし、仏滅の日と比べて避けられる傾向も一部にはあります。
●赤口(しゃっこう、しゃっく)
赤口は、漢字の通り「赤」が示す火や血のイメージから、火事や血を連想させるため、成り行きの良くない凶の日と位置付けられることが多いです。
ただし、正午(11時から13時頃)だけは吉とされ、それ以外の時間帯は凶とされるため、その時間に合わせて行事を執り行う工夫もあります。特に、勝負事や重要な決定は避けるのが無難です。
●友引(ともびき)
最後に、友引について詳しく見ていきましょう。友引は、「ともびき」と読み、「共引き」という漢字が当てられていた昔の表記もあります。
もともとは、「勝負の決着がつかず、引き分けに終わる日」を意味していたと考えられていますが、現代では「友人を引き連れていく」と解釈され、「人の運命や命を引きずる」、「災いをもたらす日」と誤解されるケースもあります。
では、なぜ「友引」が葬儀を行う日として避けられるのか、その理由について詳しく見ていきましょう。多くの方が「友引は縁起が悪い」と感じるのは、もともとの意味や風習に由来しています。
まず、最も多く耳にする理由の一つとして、「故人が友を引き連れていく」と考えられているためです。
すなわち、友引の日に葬儀を行うと、故人が最期に友人や知人を連れて行ってしまうというイメージから、縁起が良くないとされているのです。
この解釈は、死のイメージと結び付いており、葬儀やお葬式の場では忌避される傾向があります。
なかには「友引」を避ける風習が強い地域もあり、多くの葬儀社もこの日を定休日や休業日に設定しているケースもあります。
これは、地域の風習や文化の中で「縁起の悪さ」が浸透しているためです。
さらに、「縁起の良さを重視したい」「故人や遺族の気持ちを考えたときに、なるべく良い日を選びたい」と考える方々の中には、敢えて避けるという選択をする方もいます。
このように、「友引」は避けたほうが良いと広く信じられていますが、実際には絶対に葬儀を行ってはいけないわけではありません。
現代においては、やむを得ない事情やスケジュールの都合から、どうしても「友引」に葬儀を行いたい場合もあります。
たとえば、全国チェーンの葬儀会館や地域の葬儀社では、友引の日でも対応可能な体制を整えているところも少なくありません。
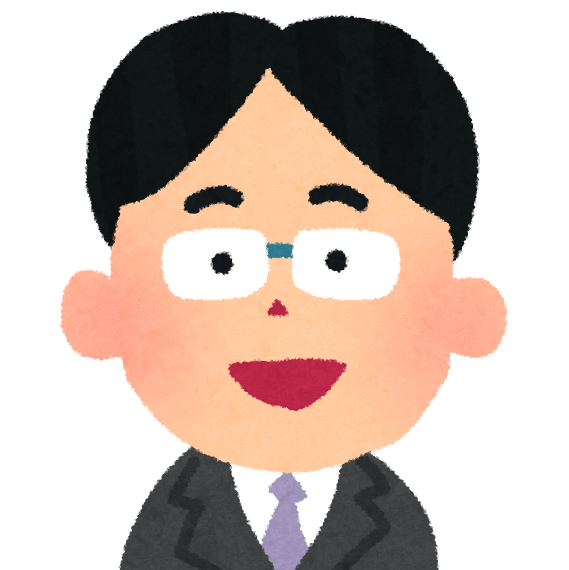
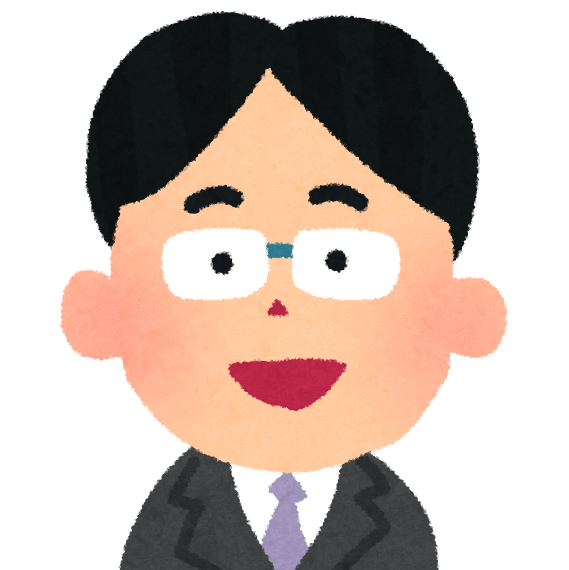
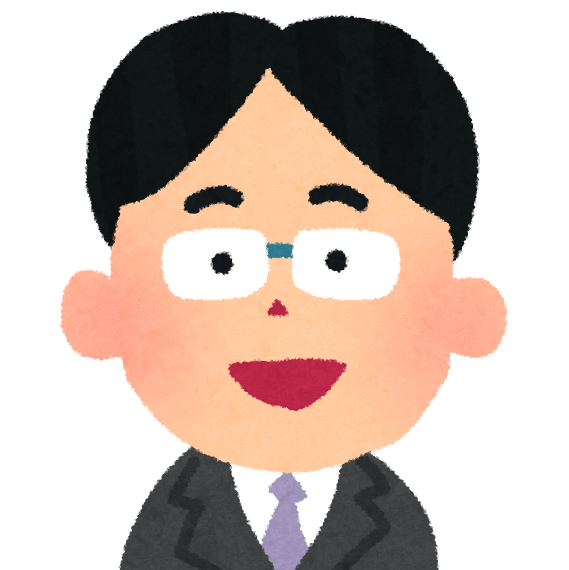
京王メモリアルでは、「多摩センター」・「調布」・「北野」の三会館ともに、友引でもご利用いただくことが可能です。お悩みの際は、遠慮なくご相談ください。
私たちスタッフがお客様のご要望に寄り添い、最適な日程調整やアドバイスをさせていただきます。
なお、友引の日に葬儀を執り行う場合、特に気をつけたいのは「お棺の中に友引人形を入れる」という風習です。
「友引人形」とは、関西圏を中心に伝統的に行われている風習の一つです。お坊さんや地域の習慣によって異なることもありますが、基本的にはお棺の中に小さなお人形やぬいぐるみを入れるものです。
この人形は、ご友人の代わりに「友引人形」が故人に同行してくれる、と信じられています。そのため、友引の日に葬儀を行う際には、遺族の方々が安心して故人を送り出せるように、この人形を入れるケースが多いのです。
友引人形の形や素材には決まりはありません。故人が生前に愛用していたぬいぐるみや、気に入っていた趣味の品を使うこともあります。
ただし、燃えにくい素材の人形やお洋服を着せたものは、火葬時に燃え残ったり、ご遺骨に付着したりする恐れがあるため注意が必要です。
「友引」が縁起の悪さから葬儀自体を避ける風潮がある一方で、「お通夜」については特に制約はありません。
お通夜は、故人と最後のお別れをするための儀式であり、悲しみや感謝の気持ちを表す時間です。そのため、「お通夜」は「友引」にあたっても、通常通り行われています。
ただし、注意点として、友引の日の翌日は火葬場や斎場が非常に混み合うことがあります。火葬のスケジュールや予約には余裕を持たせることをお勧めします。
特に、繁忙期や医療救急体制の影響もあり、火葬場の手配が難しいケースもあります。ご予定を立てる際には、スタッフや斎場の方に事前にご相談いただくと安心です。
最後に、私たちがお伝えしたいのは、「友引に葬儀を行うことは悪いことではない」ということです。
伝統的な風習や言い伝えには意味があり、多くの方々が大切に受け継いできた文化です。一方で、現代の社会や医療・葬儀の事情によって、柔軟に対応しているケースも増えています。
大切な故人さまをお見送りするにあたり、最も重要なのは、ご遺族の気持ちや宗教・宗派のしきたりなどを尊重することです。
日取りの選び方も、その一つです。お気持ちや状況に合わせて、最も良い日を選び、心を込めてお別れの儀式を執り行うことが何よりも大切です。


お電話で直接の相談や、メールでのご相談を
ご希望される方は、こちらよりお進みください。