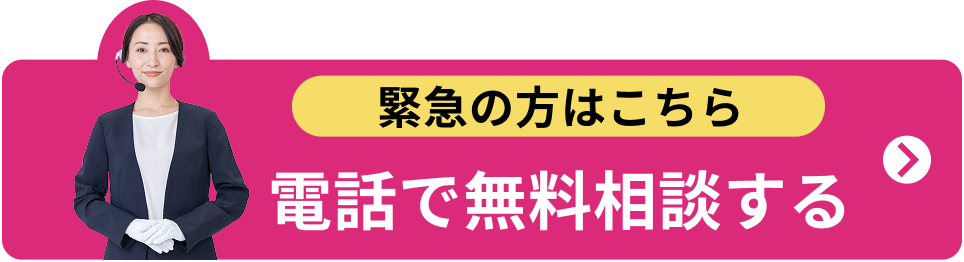
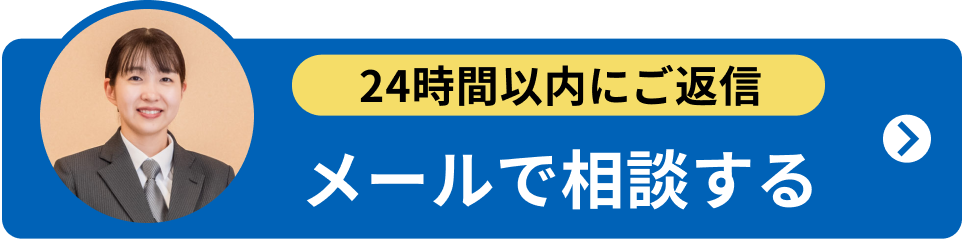

一般葬・家族葬
直葬・お別れプラン
市民葬
法要プラン

葬儀の際に火葬したご遺骨をお骨壺へお収めしますが、地域によって収骨方法やお骨壺の大きさに違いがあります。
今回はそういった収骨に関する地域差をまとめてみました。
著者|

京王メモリアル 葬祭ディレクター
お骨壺の大きさには主に「寸」という単位が用いられます。
1寸=約3cmです。お骨壺の直径の長さを表しています。
また、地域による収骨の違いですが、大きく分けるとお骨壺のサイズが7寸以上か6寸以下で収骨方法に違いがあります。
まず、7寸のお骨壺は直径で約21cm、一般的に用いられるお骨壺の中では大きいサイズになります。
こちらを使用する地域は、すべての遺骨を拾う全収骨が主流となっている地域です。
東北、関東、一部九州地域や沖縄県等が例として挙げられます。
対してそれ以外の6寸以下のお骨壺を用いる地域では部分収骨が主となります。
全収骨の場合はすべての遺骨をお骨壺へ収めるために、入りきらない大きなお骨を崩しますが、
部分収骨の場合はお骨壺に無理なく入るものだけをそのまま収めることが多いです。
また、中には陶器のお骨壺ではなく桐の箱や袋へ収骨をするといった地域があったり、
分骨といって複数のお骨壺にお骨を分けて収めることが主流な地域があったりと、
お骨壺の大きさだけではなく地域によっても様々な違いが見られます。
では、実際の葬儀になった場合、
「どの大きさのお骨壺を選択すればいいんだろう?」
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
そこで一番気にしなければならないのが、納骨先の都合です。
お墓であれば、墓石の下のカロート1の大きさによって入れられるサイズが変わりますし、
納骨堂であればそれぞれの施設によって取り決めが違いますので、予め納骨先へ確認しておくことを推奨いたします。
まだ納骨先も何も決まっていないという方は、お骨壺に合わせて納骨先を選ぶことも可能です。
なお、手元供養としてお骨を手元に残す場合や、複数個所へ納骨するようであれば分骨する必要があります。
そのため、予めご家族のご意向を固めておくと良いかもしれませんね。

お電話で直接の相談や、メールでのご相談を
ご希望される方は、こちらよりお進みください。